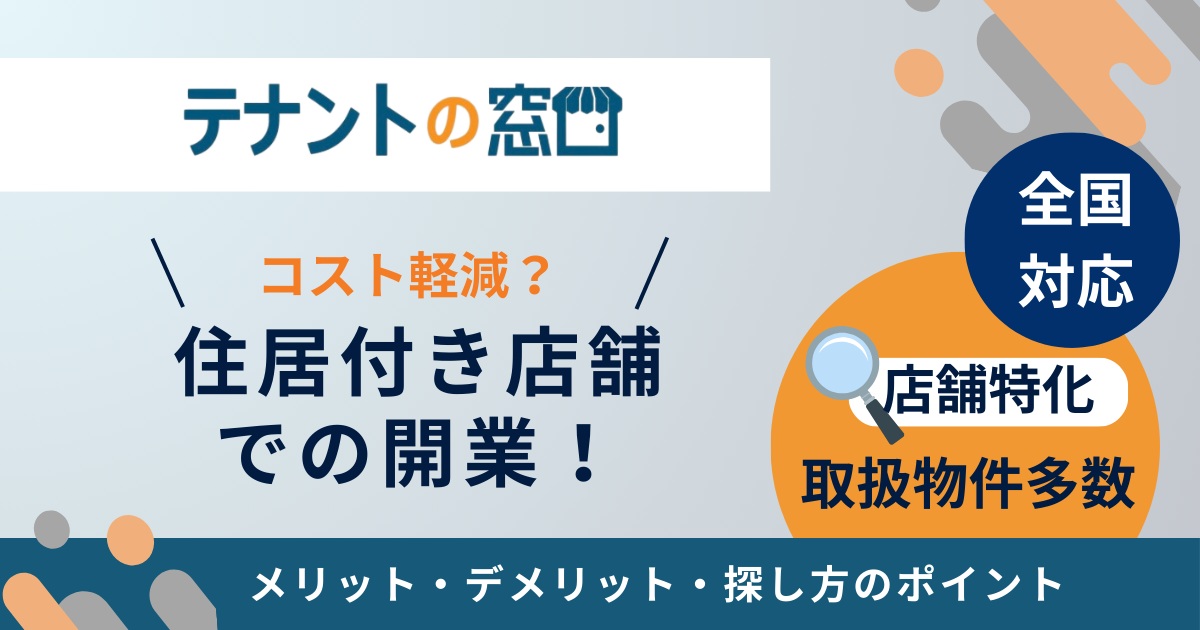「自宅とお店を別々に借りると、家賃や固定費がかさむ…」そんな悩みを解決するひとつの方法が「住居付き店舗」です。
住居と店舗をひとつの契約でまとめられる分、コスト面でのメリットがある一方で、特有のデメリットもあります。
この記事では、住居付き店舗を「賃貸」で利用する場合のメリットとデメリット、そして物件探しのコツをわかりやすく解説します。
住居付き店舗とは?
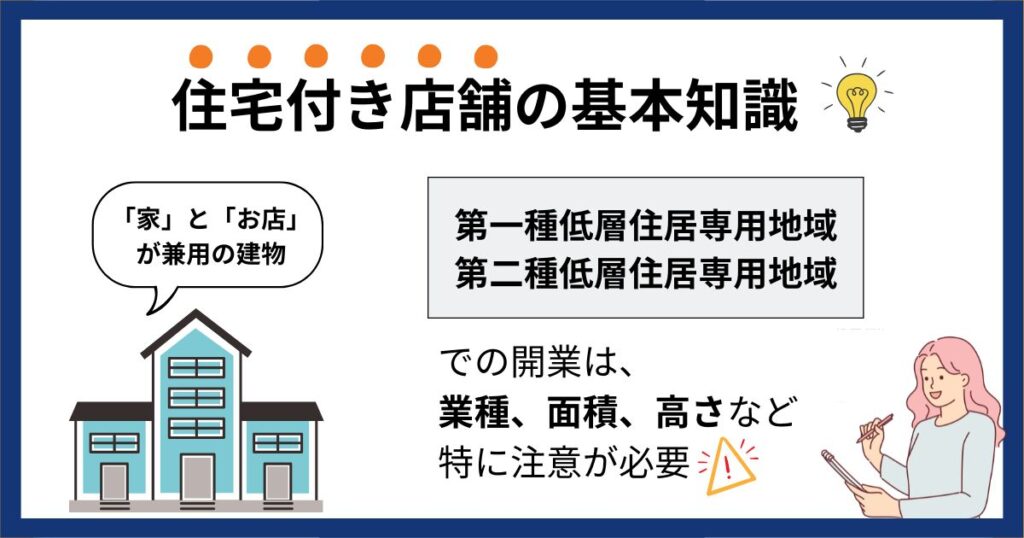
まずは「住居付き店舗」がどのような物件を指すのか、また注意点について整理しておきましょう。
定義と特徴
住居付き店舗とは、同じ建物内に「住居」と「店舗」両方がある賃貸物件のことです。
代表的なタイプは、
- 1階部分を店舗、2階以上を住居とする形
- 1フロアを仕切って半分を店舗、もう半分を住居として利用する形
です。「店舗併用住宅」や「店舗付き住宅」と呼ばれる場合もあります。
最近では、サロンや教室など、生活と事業を両立させたい小規模事業者に人気があります。
用途地域の注意点
物件選びで注意すべきなのが、都市計画法で定められた「用途地域」です。
第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域はもっとも厳しい用途地域で、制限がかなり細かく決められています。
・店舗利用は「日用品販売店舗や事務所」に限定
・床面積の合計は150㎡以下
兼用住宅の場合、上記に加えて、
・建物の延床面積の半分以上が住居部分であること
・店舗・事務所部分の床面積が50㎡以下であること
とされます。また、高さなどの制限もあるため、2階建て以下などに限定されるケースもあります。
第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域も、低層住宅の良好な住環境を守ることを目的とした用途地域です。ただし、第一種よりは制限が緩くなります。
・店舗や事務所の利用が可能(ただし日常生活に供する規模に限られる)
・床面積の合計は150㎡以下
・小規模な飲食店なども許可される場合がある
第一種と同様に「建物の延床面積の半分以上が住居部分であること」「店舗・事務所部分の床面積が50㎡以下であること」が条件で、高い建築物が建てられないケースがあります。
その他の用途地域
その他にも、注意すべき用途地域があります。
| 用途地域 | 注意点 |
| 工場専用地域 | 住居自体が建てられないエリアのため、基本的には併設不可。 |
| 準住居地域 | 店舗や住宅も建てられ自由度は高いが、工場の騒音や振動で住環境に注意が必要。 |
| 商業地域 | 繁華街や駅前に多く、住居としては騒音・日照・治安面が課題。 |
住居付き店舗を借りるメリット・デメリット
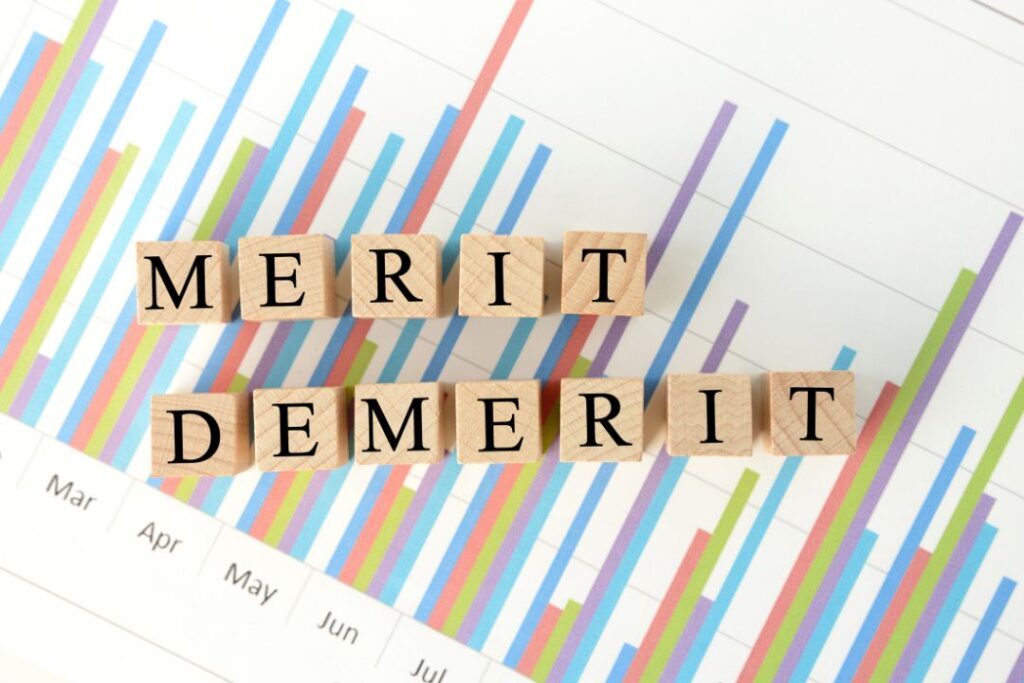
住居付き店舗は「コスト削減」という大きなメリットがあります。
しかし、メリットだけに目を向けて契約してしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうかもしれません。利点と注意点をあわせて確認しておきましょう。
メリット
住居付き店舗を借りる最大の魅力は、生活と事業をひとつにまとめられる点にあります。
具体的には次のようなメリットが挙げられます。
・家賃をまとめて抑えられるため、開業時の固定費を大きく節約できる
・通勤が不要になり、仕込みや営業準備など時間を効率的に使える
・家族経営や小規模事業に向いており、生活と仕事を両立しやすい
店舗経営をやめたとしても、住居部分のみを活用できる場合があります。事業リスクを考慮したとき、万が一に備えられる安心感につながります。
デメリット
一方で、生活と事業が重なるからこそ生じるリスクや制約もあります。借りる前に、次のような点を理解しておきましょう。
初めての開業で見落としやすい点もあるため、契約前に一つひとつ確認しておくことが大切です。
住居付き店舗で開業するための届出

「子育てをしながら、自宅でネイルやエステのサロンを始めたい」
近年、このように育児をしながら自宅での開業を希望する女性が増えています。マイホームならあまり気にすることなく始められますが、賃貸の場合は事情が少し違ってきます。
届出の前にオーナーへ確認する
賃貸で住居付き店舗ビジネスを行う場合、行政への届出よりも先に大切なのがオーナーへの確認です。賃貸契約の用途に「住居」としか記載がない物件では、店舗利用が禁止されていることも多くあります。
たとえば美容系サロンの場合、集客のためにポータルサイトへ掲載することで、無断利用が発覚するケースもあるので注意しましょう。
開業に必要な届出
個人事業主として開業する場合は、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。青色申告を選びたい場合は「青色申告承認申請書」も一緒に提出しましょう。
店舗部分が20㎡を超える場合や、不特定多数が出入りする場合は消防署へ「防火対象物使用開始届」の提出も必要になります。
ネイルやエステであれば特別な資格は不要ですが、美容室や理容室を兼ねる場合は「美容所登録」が必須です。
そのほか、飲食系であれば保健所への「食品営業許可」や「菓子製造業許可」が、中古品の販売であれば管轄の警察署への「古物商許可申請」が必要になります。
住居付き店舗のトラブル

住居付き店舗は、「店舗だけ」「住居だけ」の物件にはない特有の問題に直面することがあります。
老朽化による立退き
代表的なのは、建物が古くなって危険だと判断されると、大家から「立ち退いてほしい」と求められることです。普通の店舗であれば移転すれば済む話ですが、住居付き店舗の場合は家とお店を両方同時に失うことになります。
引っ越し先を探すときも、条件を満たす物件がなかなか見つからないのが悩みです。とはいえ、退去日が決まっている以上、ずっと探し続けるわけにはいきません。次の住まいか店舗、またはその両方の条件を妥協して選ばざるを得ないのが現実です。
長年住み慣れた地域を離れると、常連客とのつながりや子どもの通学環境にも影響してしまいます。
曖昧な修繕負担
住居付き店舗では、建物の修繕や設備の故障をめぐって「どこまで大家の負担で、どこから借主の負担なのか」が曖昧になりやすいという問題があります。
通常の住居利用であれば大家が修繕・交換するのが一般的ですが、店舗利用の場合は「事業利用による消耗」と見なされ、借主に修繕費を請求されることも。
契約書に修繕負担の範囲が明記されていないとトラブルになりやすいため、事前に取り決めを確認しておくことが重要です。
住居付き店舗の探し方と注意点
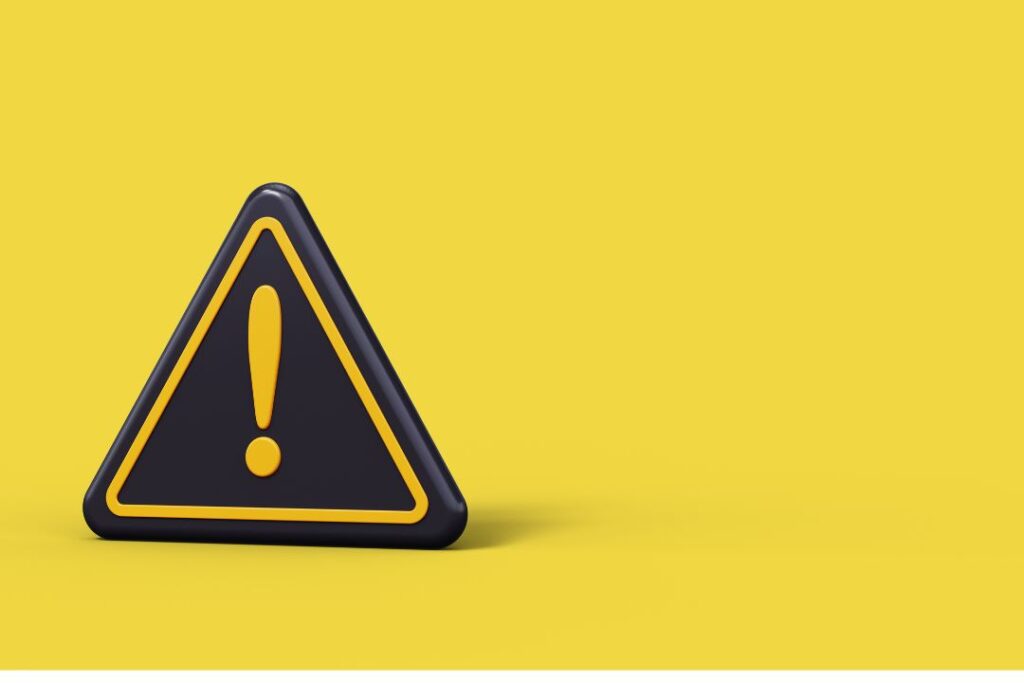
そもそも住居だけの賃貸市場でも「戸建て賃貸」は希少で人気が高い傾向があります。そのうえ店舗スペースを備えた物件となればさらに限られてくるため、どう探すかが重要です。
ポータルサイトを活用
大手の不動産ポータルサイトでは「住居付き店舗」「店舗付き住宅」といったジャンルで探すことができます。ただし、掲載数は多くないため、効率よく探すなら店舗専用のポータルサイトを活用するのがおすすめです。
ちなみに、全国対応の弊社では住居付き店舗のほか、幅広い事業用物件を検索できますので、ぜひご活用ください。

地域の不動産会社に相談
地域密着型の不動産会社は、ネットに出ていない住居付き店舗を取り扱っていることもあります。
地方や郊外のように不動産会社自体が少ないエリアでは、直接現地で相談するのが有効です。大手仲介会社は、動きが早く、利益が出やすい都会の物件を優先しがちです。
その分、現地で活動している不動産会社に直接相談した方が、売主とのツテなどから埋もれていた物件に出会えるチャンスが高まります。
事業用不動産に詳しい仲介会社を活用
ポータルサイトと同じように、契約時にも事業用不動産に詳しい仲介会社を活用することをおすすめします。
「店舗兼住居」という特殊な契約は、通常の住宅賃貸に比べて確認事項が多いため、事業用不動産に強い会社に相談することでスムーズに契約を進められます。
希少物件はスピード勝負
住居付き店舗は希少性が高いので、条件に合う物件が出たら早めに申し込む必要があります。
すぐに申し込めるように、あらかじめ物件や契約に関する知識を身につけておくと安心です。
まとめ

住居付き店舗の賃貸は、家賃を抑えて開業できる魅力的な選択肢です。
しかし、用途地域や契約条件、業種制限など注意点も多いため、事前の準備が大切です。
物件数が少なく競争も激しいため、ポータルサイトでの検索と地域の不動産会社への相談を併用し、条件に合う物件をいち早く押さえることが成功のカギとなります。