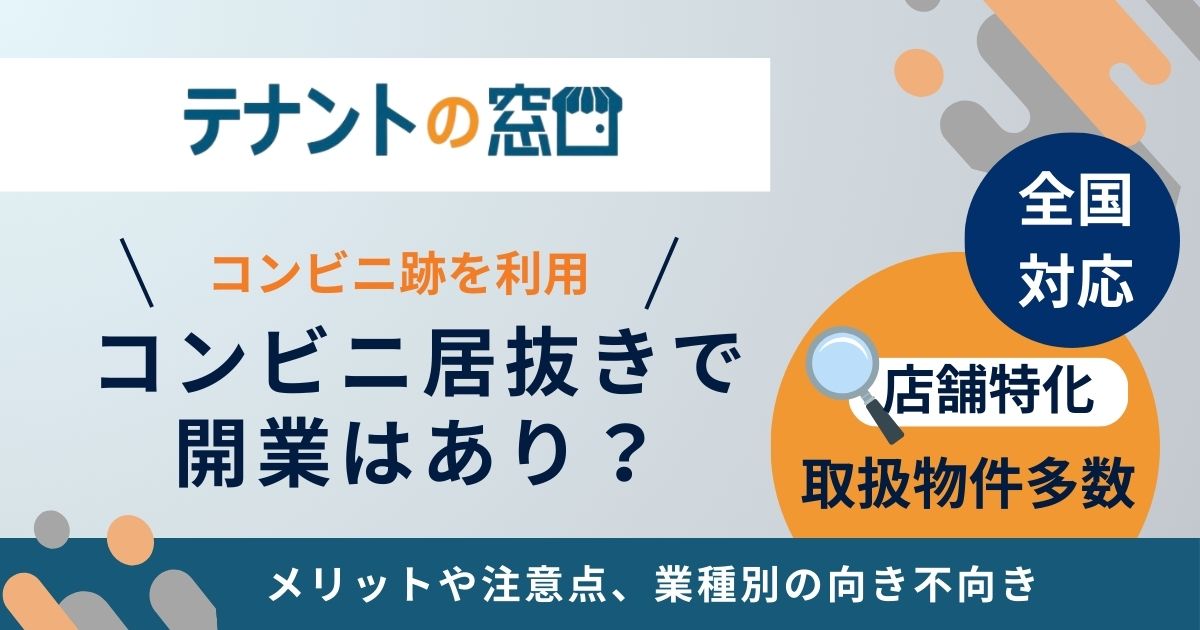「もしかしてこの物件、使えるかも。」
テナント探しの途中で、コンビニの空き店舗を見てそう感じたことはありませんか。設備や什器(じゅうき)が揃い、使いやすい点から居抜き物件の中でも人気があります。
ただし、店舗の広さは限られており、業種によっては動線が合わないこともあります。
そこで本記事では、コンビニの居抜き物件がどんな業種に向いているのか、また逆に不向きなケースは何かを、具体例を交えて解説します。
コンビニ居抜き物件とは?

コンビニ跡の居抜き物件は、前のテナントが使っていた内装や設備をそのまま借りられるケースが多く、工事費用を抑えられる可能性があります。
まずは、物件の特徴や立地からみる傾向、市場動向について解説します。
コンビニ跡の居抜き物件に多い特徴
元コンビニは、営業に必要な基本的な「土台」が揃っています。
- レジカウンター
- バックヤード
- フライヤー
- 空調
- 照明
- トイレ
- 手洗い 等
動力電源や分電盤の容量が大きめで、冷蔵・冷凍機器を置ける前提になっていることが多いです。また、モップや洗浄機での清掃を想定した床材が残っているケースが多く見られます。
店内は長方形で奥行きがあり、棚を並べる前提の動線になっています。出入口やトイレの位置、バックヤードの扉など、動かしにくい「固定点」があるのも特徴です。
【関連記事】居抜き物件とは?開業前に知りたいメリット・デメリット、失敗事例 | てなまど
コンビニ跡の立地傾向
コンビニ跡に多くあるのは、幹線道路沿いや信号のある交差点付近、いわゆる「角地」です。車の流れは多く、視認性も高いため、朝夕の通勤・通学の時間帯は特に強い立地です。
他にも、住宅街の入り口やスクールゾーン近くでも多く見られます。また、駅前には小型店跡が点在します。
いずれの立地でも共通するのは、「人(または車)の流れが読めること」。横断歩道の位置、信号待ちの滞留、バス停や横断デッキとの関係など、「立ち止まる理由の有無」が明暗を分けます。
コンビニの店舗数動向
国内のコンビニ市場は、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3社が大半を占めています。近年のコンビニ店舗数は、閉店と新規出店がほぼ拮抗しており、大きな増減は見られません。入れ替わりはあるものの、全体の規模は安定した水準を維持しています。
| 時期 | コンビニ店舗数 |
| 2024年12月 | 55,736 |
| 2023年12月 | 55,713 |
| 2022年12月 | 55,838 |
| 2021年12月 | 55,950 |
| 2020年12月 | 55,924 |
| 2019年12月 | 55,593 |
| 2018年12月 | 55,743 |
(出典:一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会「過去のコンビニエンスストア統計調査」)
これは各社が店舗数を競うように増やし続けてきた結果ともいえますが、ここ数年は方向性が変わってきました。近年、海外展開に力を入れる一方で、国内では新規出店よりも既存店舗の売上アップや収益改善を重視しています。
その流れの中で、売上の採算が取れない店舗は整理の対象になりやすく、将来の人手不足も相まって閉店が進んでいくと考えられます。今後、街中でコンビニの空き店舗を目にする日が、今よりも多くなるかもしれません。
コンビニ居抜き物件のメリット

立地・設備ともに高いアドバンテージのある元コンビニ物件は、工夫次第でオープン直後から集客につなげられます。ここでは代表的なメリットを整理します。
立地条件が良いケースが多い
コンビニはもともと「来店しやすさ」を重視して出店されており、車でも徒歩でもアクセスしやすい場所が多いのが特徴です。
人や車の流れが安定しているうえ、商圏人口や利用者層も比較的明確で、時間帯ごとの人の動きも予測しやすい点が強みです。こうした条件をクリアしたうえで出店されているため、「元コンビニ=立地力にお墨付き」といえます。
駐車スペースが確保されている
多くのコンビニは、敷地内に複数台分の駐車スペースが用意されています。そのため、遠方からの来店やまとめ買いをする顧客も取り込みやすくなります。
回転率の高さと駐車場の利便性が相まって売上に直結しやすいのもメリットです。
視認性を高めやすい
コンビニ跡地は大きなガラス面や明るい照明、看板用のポールなど、遠くからでも店舗が目に入りやすい造りになっています。
特にロードサイド立地では、この視認性の高さが強みです。看板や外装デザインを自社仕様に変えるだけでも、新規顧客へのアピール効果が高まります。
トイレなどのインフラが整っている
水回りや空調、電気容量など、日常営業に必要なインフラが揃っている場合が多いのも元コンビニ物件の特徴です。
特にトイレは、開業時に新設すると大きなコストと工期がかかりますが、すでに利用可能な状態であれば大幅な負担軽減につながります。
コンビニ居抜き物件のデメリット

コンビニの居抜き物件はとても魅力的ですが、もちろんメリットばかりではありません。以下で代表的なデメリットを解説します。
間取りが特殊で業種によっては合わない
元コンビニ物件は、通路幅や動線も物販向けに作られています。そのため、スペースの取り方に制約が生じやすいのが難点です。
レイアウト変更の自由度が低いテナントは、個室を区切る必要のあるサービス業には合わない場合があります。
テナントに「コンビニ感」が残る
外観や内装には、前店舗の印象が色濃く残っているケースがあります。看板跡や間取り、床や天井材、照明の配置など、いわゆる「コンビニらしさ」が残ってしまうことも少なくありません。
業種やブランドイメージに合わない場合は、外装や内装の大幅な改装が必要になる可能性があります。
敷地が広く賃料が高くなりやすい
元コンビニ物件は、駐車場や搬入口を含めて敷地面積が広く、その分だけ家賃も高くなることがあります。ロードサイド型の飲食店やドライブスルーを備える業態なら、この広さがそのまま集客力につながります。
しかし、徒歩での来店が中心となる場合、駐車スペースを使いきれず、広さに見合わない賃料を払い続けることになりかねません。
業種別・コンビニ居抜きの向き不向き
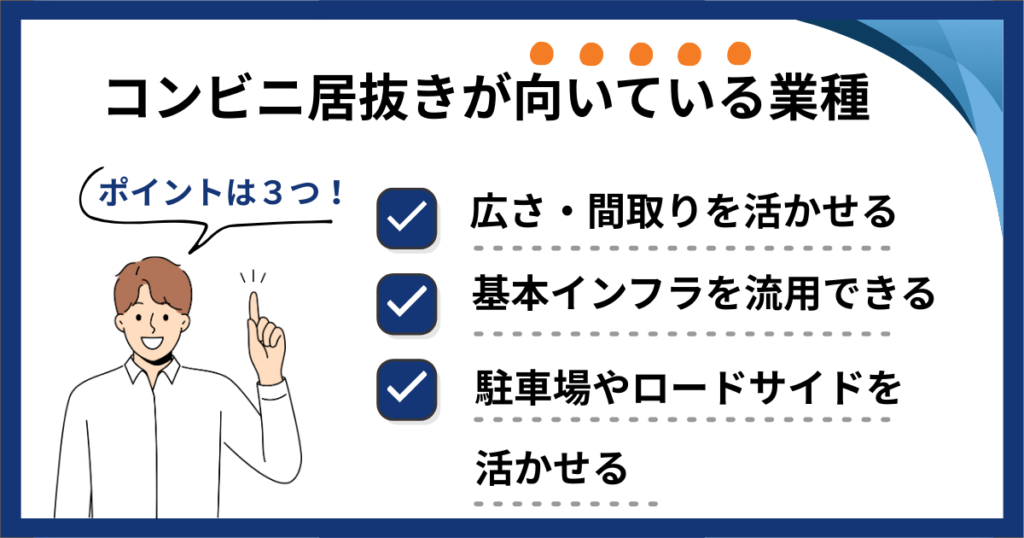
では、具体的にどのような業種がコンビニの居抜きとして向いているのでしょうか。向いている業種とそうでない業種について、それぞれまとめました。
向いている業種
| 業種 | ポイント |
| ファストフード・軽飲食 | 厨房やカウンター、冷蔵・冷凍設備が活かせる。小規模な短時間滞在型の店舗を推奨。 |
| テイクアウト専門店 | 駐車場やロードサイド立地を活かしやすく、車来店が見込める。ドライブスルーも要検討。 |
| ドラッグストア・ミニスーパー (生鮮・惣菜・日用品の小売) | 什器や冷蔵設備をそのまま利用できるため、開業しやすい。 |
| コインランドリー | 24時間営業にも対応しやすく、水道・電気容量が確保されている場合が多い。 |
| フィットネスジム | ガラス面や照明による視認性の高さが集客に有効。駐車スペースがあるため郊外型ジムとも相性が良い。 |
向いていない業種
| 業種 | ポイント |
| 多席型飲食店・重飲食 (居酒屋・レストランなど) | 厨房や座席レイアウトを一から作り直す必要があり、既存設備がほとんど活かせない。排気設備も追加で必要。 |
| 美容室・理容室 | 大規模な給排水工事や間仕切りの設置が必要で、初期投資が高額になりやすい。レイアウトにも工夫が必要。 |
| 学習塾・教室 | 大きなガラス面や開放的な間取りがプライバシー確保に不向き。個別ブースや防音施工などで改装費がかさむ。 |
| 医療・介護施設 | 専用の動線(待合室や診察室への導線)や設備(医療用水回り、バリアフリー化)が不足し、大規模工事が避けられない。 |
良いコンビニ居抜き物件を見極めるポイント

見た目が整っていても、条件次第では思わぬ追加コストや集客難に直面することもあります。成約前に必ず押さえておきたい4つの視点を一緒に考えてみましょう。
①前テナントの撤退理由
外から見える事情だけで判断せず、撤退の背景を具体的に把握することが重要です。
「オーナーの高齢化・事業譲渡」など物件そのものに起因しない理由であれば、さほど問題ありません。一方、「売上不振」「交通規制の変更」など立地や需要そのものに関わる要因であれば要注意です。
コンビニは商圏分析が精密な業態なので、大手チェーンの撤退理由は、将来の集客を測る有力なヒントになります。
②設備状態
設備チェックでは、現状の可動だけでなく耐用年数や性能の残りも確認が必要です。
冷蔵・冷凍ケースや空調機は耐用年数を超えると電気代が上がるほか、故障時の修理部品が入手困難になることもあります。
さらに、動力電源容量や給排水設備が自分の業態に足りているかも確認しましょう。例えば、フィットネスジムやコインランドリーなど水道・電気負荷の大きい業種では、契約後に容量不足が発覚すると大規模な工事が必要になります。
③契約条件
賃料や敷金の額だけでなく、「造作譲渡契約」の内容にも目を通すべきです。
譲渡範囲が曖昧だと、「引き渡し時に残っていると思っていた設備が撤去されていた」というケースもあります。また、賃貸借契約に重い原状回復義務が設定されていると、退去時に高額な撤去費用を請求されることもあります。
ロードサイド物件の場合は、看板における高さ制限といった使用条件も細かく調査・確認が必要です。
【関連記事】テナントの原状回復はどこまで必要?範囲・費用・業種別のポイント | てなまど
④用途地域や制限
コンビニ跡地だからといって、どんな業種でも営業できるわけではありません。
都市計画による用途地域の制限で、飲食や物販は可能でも、特定のサービス業や大型店舗は許可が下りない場合があります。
郊外立地では、開発許可や景観条例、広告物規制が意外なネックになることもあります。事業に支障がないか、役所や不動産会社を通じて、必ず契約前に確認しましょう。
まとめ
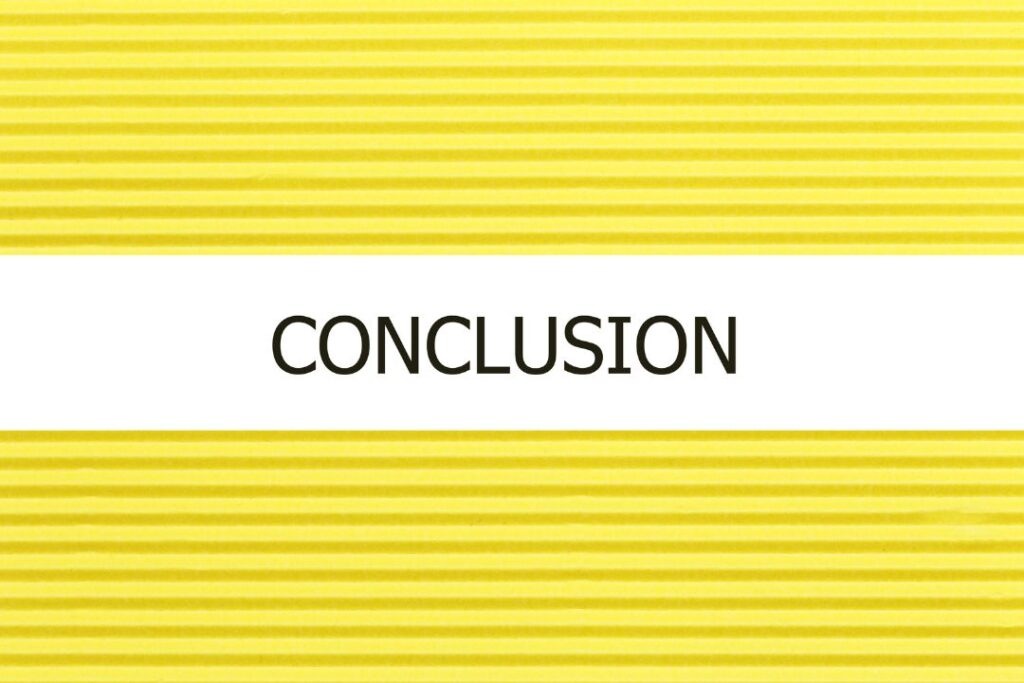
コンビニ居抜き物件は、立地や設備をそのまま活かせる分、スタートダッシュを切りやすい反面、業態との相性を誤ると改装費や運営負担が重くのしかかります。
物件の背景や設備の寿命、契約条件、地域の規制まで丁寧に洗い出すことで、想定外の出費や集客難を防げます。
「安いから」「立地が良さそうだから」だけで飛びつかず、自分の事業が長く根付く条件かどうかを見極めることが、成功の近道です。